 (11〜20)
(11〜20) (11〜20)
(11〜20)
| (11)大航海時代の風雲児たち | 飯島幸人 | (2004/11/14) | ||
| (12)鄭和の南海大遠征 | 宮崎正勝 | (2004/11/24) | ||
| (13)海嶺 | 三浦綾子 | (2004/12/18) | ||
| (14)海の夜明け | 白石一郎 | (2005/01/09) | ||
| (15)楽園考古学 | 篠遠喜彦・荒俣宏 | (2005/01/30) | ||
| (16)青い地図 | T・ホルヴィッツ(山本光伸訳) | (2005/04/03) | ||
| (17)無人島に生きる十六人 | 須川邦彦 | (2005/06/16) | ||
| (18)海のサムライたち | 白石一郎 | (2005/06/28) | ||
| (19)アメリカ彦蔵 | 吉村昭 | (2005/10/01) | ||
| (20)督乗丸の漂流 | 川合彦充 | (2005/10/26) |
| (11)大航海時代の風雲児たち | ||||
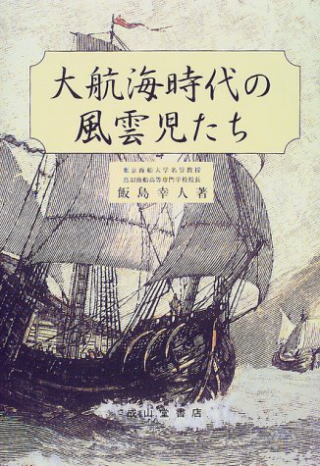 |
著 者:飯島幸人 発 行:成山堂書店 |
|||
|
大航海時代といわれる時代に活躍した人たちの物語は、何時読んでも胸躍らせられるワクワクした冒険談に満ちています。いわば時代の先駆者達ですから、当然といえば当然なのかもしれません。この本は鳥羽商船高等学校長だった人の書いたものなので、まるで教科書のような要領よい取りまとめ方で、ちょっと面白味に欠けるきらいがありますが、エンリケ王子に始まるヨーロッパの拡大をコロンブス、マジェラン、ドレイク、クック、更には永楽帝時代の鄭和に至るまで取り上げていますから、走り書きのような記述になってしまったのも無理ないのかもしれません。私は以前、伝記作家シュテファン・ツヴァイクのマジェランを読んだことがありますが、今回この本を読んでみて、マジェランに関しては要約を確認した気持ちになりました。その意味からは各人の伝記を読んでからもう1度この本に接するとよいかもしれません。しかし、大航海時代の歴史を簡単に知るという点では、充分に役に立つことでしょう。 (by 徳子) |
||||
| (12)鄭和の南海大遠征 | ||||
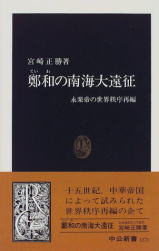 |
著 者:宮崎正勝 発 行:中公新書 |
|||
|
前回ご紹介した“大航海時代の風雲児達”の中に、東洋における航海者、鄭和の記載があったのに興味を持ち、読んでみました。この本では大航海時代を第1次から4次まであったとしています。私達が通常思い至るヨーロッパ世界の大航海時代は第3次大航海時代と位置付け、ヴァスコ・ダ・ガマがインドに到達した時よりも約1世紀早く、カリカットにまで航海した鄭和(ていわ)の遠征を第2次大航海時代としています。8世紀後半以降、ダウ船といわれるムスリム商人の交易船がインド洋を行き来し始めた頃が新しい時代、大航海時代の始まりで、次いで10世紀に入ると中国の大型ジャンクがアジア海域を交易し始め、ダウ交易圏と接触し第2次大航海時代に突入するのです。モンゴル帝国が衰退し明王朝が起こった15世紀、鄭和は第2代明皇帝永楽帝の命を受けて、明朝の威光を南海各地各国に示すべく大遠征に出掛けて行くのです、それも7回に亘って。鄭和の船団は宝船(ほうせん)と言われる大型艦船60隻余が中心となり200隻近い小型船が随行する大掛かりなもので、2万7千人が乗り組んでいました。白髪三千丈の表現がある中国、と思うとちょっと眉唾に考えたくなる規模なのですが、間違いの無い史料に基づいているとのこと、スゴイ過去があったことになります。鄭和の生い立ち、7回各航海の詳細、そしてその背景にあった中国史とともに、造船技術から航海術、この時代に既に知られていた地理知識や海図のこと、私の勉強不足を驚かす新しいことが一杯記載されているので、一生懸命読みましたが、中国から見た外国の地名が漢字で記載されていること、現在では変わってしまっている場所や名前に、読んでいて少し取っ付き難い思いをしました。 (by 徳子) |
||||
| (13)海嶺 | ||||
 |
著 者:三浦綾子 発 行:朝日文庫、角川文庫(写真) |
|||
|
知多半島美浜町小野浦の弁財船(千石船)宝順丸が江戸へ向かう途中、遠州灘で嵐に会い漂流の結果、悲惨な運命にもてあそばれた3人の物語です。最初14人いた乗組員が漂流中に次々と死に絶え、岩吉、久吉、音吉だけが残り、バンクーバー近くに漂着後、インディアンに捕らえられ彼等の奴隷になりますが、ハドソン湾会社に救出された後、日本への帰国を切望しながら最終的には叶わなかった経緯を描いています。この話は実録に基づくもので小説の形をとっていますが、3人の心情を思いやって、故郷を偲ぶ会話の多いことが読み易くしているようです。春名徹氏の「にっぽん音吉漂流記」(こちらは史実を忠実に書き述べた実録書で、音吉だけではなく当時の多くの漂流者についても言及している)によれば、彼等が日本への帰国を願い、そしてそれを叶えようとした周囲の人々には、日本との通商を望んでこの3人を利用しようとした駆け引きにも似た動きがあったようですが、この本ではそういった煩わしい出来事は省いて、3人の側からの思い、行動を描いている点も物語として読ませることになっているのかも知れません。アメリカ西海岸のポートランドから日本へ帰るのに、ハワイ経由ホーン岬を回ってロンドンに寄り、その後インド洋を渡ってマカオへ到着という世界一周の旅を余儀なくされた経緯や、マカオからは、武力を誇示するのではなくわざわざ大砲を下ろして平和な接触を求めてモリソン号で日本へやってきた理由などにも拘わらず、一応の納得は出来るでしょう。小説は、モリソン号が文政8年に出された外国船無二念打ち払い令により浦賀においても、鹿児島においても砲撃されて音吉達の帰国が叶わず、無念この方ないままマカオへ引き返すところで終わっています。この日本へ受け入れられなかった漂流民たちのその後の消息はかなり分かっていて、上海である程度の成功を収めた音吉は「14歳の歳に故郷を離れ、親には大変な心配をかけてしまった。せめてもの恩義を漂流民を日本へ送り返すことで償いたい」と上海にやってきた漂流者たちを支えています。美浜町の町長は、郷土から出たいわば歴史の中の偉人とも言える音吉漂流の事実を熱心に勉強されているそうです。来年の愛知万博には、音吉の辿った航跡をイメージした、チェコのティレクさんという画家の作品が出品されるとか、実際に現在、美浜町の野間の少し南には、ティレク美術館がオープンしていますが、音吉の生涯には、感銘するしかないのかもしれません。 (by 徳子) |
||||
| (14)海の夜明け | ||||
 |
著 者:白石一郎 発 行:徳間文庫 |
|||
|
暮に中公新書、藤井哲博著の長崎海軍伝習所を見つけ、以前に呼んだこの本をもう1度読み返してみました。「海の夜明け」では塩飽諸島出身者の水夫達を主人公にして、いわば庶民の立場からの日本海軍がいかに誕生したかを描いています。これに対して藤井著は正統の歴史を述べていて、伝習生は旗本出身や幕府の役人たち、いわゆるオフィサーにあたる後の幕府重臣や明治新政府を担うことになるエリートたちがずらり名を述べられているのを対比してみようと思ったからでした。正史記述では水夫については「水主(かこ)は塩飽諸島出身者が多かったがこれは明らかに人選の誤りであった。」とばっさり切り捨て、水夫教育についても数行しかありません。人選の誤りは和船の操船に慣れた水夫たちが西洋型横帆の扱いに馴染めなかったためで、白石一郎もこれに触れ、主人公となって描かれている鶴松は塩飽・本島の庄屋の家で下男の息子として暮らしていたため、全くフネには経験なかったのが反って幸いして、一等水夫長になることが出来ました。この鶴松を始め準主人公の仙三郎や辰之助が実在したかどうかはフィクションなので、ないと思われますが、少なくとも海軍伝習所では、かくありなんと思われる出来事があったであろうことを知ることが出来ます。オランダから派遣されてきた教授陣の顔ぶれや授業内容の詳細は、どちらの本も同じように書かれていますから、史実としての内容は間違いないことでしょう。面白いと思ったのは咸臨丸で、日本船初めての外国行き軍艦艦長を勤めた勝海舟が、私達のイメージとして英雄的に思われていたのに、藤井氏は完全に落第生だったとの烙印を押し咸臨丸での船長責任も果たされていなかったと書いているのです。でも白石本では成績は確かにダメだったものの人纏めがうまく、習慣や風土の違いからくるオランダ人教師達と伝習生たちとの仲立ちを果たしたし、咸臨丸では船酔いに弱かったのだろうと庇っているのは、著者の勝海舟に対する尊敬の念があるからだろうと推察できました。日本海軍誕生の経緯のみならず、異文化を受け入れるに当たって、人それぞれの感受感があるのを知るのも面白いと言える本だと思います。 (by 徳子) |
||||
| (15)楽園考古学 | ||||
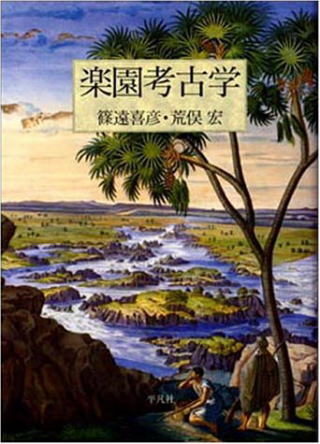 |
|
|||
|
ハワイを頂点に南東イースター島と南西ニュージーランドの各点を結んだ3角形がポリネシアと言われる海域及び島々で、ここにおける考古学の研究成果を述べている本です。タテオ・シノトこと篠遠博士(タテオはタヒチ語でドクターの意)はハワイ・ビショプ博物館の特別研究員ですが、永年ポリネシア各地の遺跡発掘を通して、ポリネシアの島々では知らない人はいないと言われるほど、有名な人だそうです。子供の頃、庭から出た土器に興味を持ったことから考古学の道に進んだのですが、ひょんなことから、太平洋の虜になってしまいました。アメリカに行き研究するつもりが、途中下船したハワイで、遺跡発掘を手伝ううちに大量に出てきた釣針に興味を持ち、それまで誰も目に留めなかった釣針を収集、分類することで遺跡の年代測定から人々の移動までも分かることを証明したのです。彼の最大の偉業は、タヒチ・ファヒネ島で大型カヌーを発掘したことでした。ジェームス・クックがタヒチを訪れた時、大型カヌーで歓迎されていますが、正にポリネシアには人々が島から島へと移動した道具のあったことを実証したわけです。また彼は、遺跡の修復にも努め、特にマラエ(イースター島ではアフ、モアイはアフの上に立っている。ハワイではヘイアウ)と言われる神聖な儀式執り行いの祭壇を復元することに力を注いできました。これは文化遺産としての遺跡を子供達に残してやりたいとの思いからだったそうです。この本は篠遠・荒俣両氏の対談の形で綴られおり、写真や挿絵も多く、読みやすいと言えるでしょう。実は先回のシャングリラのキャビンでテレビを見ていた時、ファヒネ島における篠遠博士の映像が流れました。あこがれのクルージングゲレンデ、ポリネシアのことは是非知って欲しい思い、紹介しようと再読した本なのですが、南太平洋クルーズを前にして私自身が再確認したからだったかもしれません。 (by 徳子) |
||||
| (16)青い地図(キャプテン・クックを追いかけて) (上・下) | ||||
 |
著 者:トニー・ホルヴィッツ、山本光伸訳 発 行:バジリコ株式会社 |
|||
|
副題にあるように、ジェームス・クック船長の太平洋を股にかけて航海した跡を、実際に辿った物語です。著者がこの行動を決意した動機にはクックが第1回の航海に使用したエンデヴァー号の複製が造られ、シアトルからバンクーバーまで乗船したことで、当時の現実をある程度体感出来たことがあるようです。キャプテン・クックが訪れたタヒチから始まり、南太平洋の島々を訪れながら、クックの痕跡がどのように残っているのか、ゆかりの人々や由緒を尋ねてクックの書き残した日誌と照らし合わせる手法を取り、ホルヴィッツが訪れた現地では、現状への観察と感想が綴られ、挿話の形でクックの日誌から想像される当時の様子が書かれていますので、単なる紀行文ではなく、洞察の深い文章が次から次へと興味を引き起こしてくれます、とても読み応えある本と言えるでしょう。特に私の場合は今回のぱしっふぃく・びーなすによる航海で、クックが寄港した島々に行ったせいもあり、1段と興味深く感じたのかも知れません。キャプテン・クックは3回にわたり述べ10年の大航海でおよそ32万キロを航行し、白紙だった太平洋のチャートを得意だった測量の技を発揮して書き上げたことには、驚嘆に値するといっても過言ではないと思います。そしてこの本ではその偉大なる業績を知るだけではない面白さがありますから、是非読んでほしい1冊です。 (by 徳子) |
||||
| (17)無人島に生きる十六人 | ||||
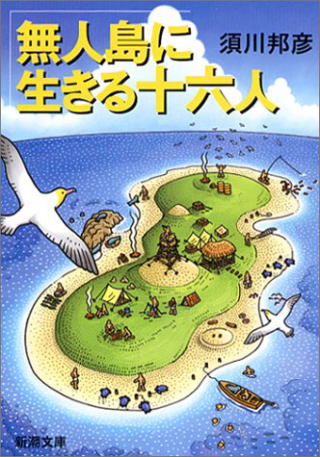 |
著 者;須川邦彦 発 行;新潮文庫 |
|||
|
「新潮文庫の冒険記」リストにこの本を見つけました。少年向けの冒険小説かと思ったのですが、明治32年にミッドウェー島近くで遭難した帆船実録談で、いかに無人島で過ごしたかを、船長自身が物語っているものです。後にこの船長は東京高等商船学校の実習船教官となり、その時の実習生だった著者が聞き及んだ話を書き纏めました。龍睡丸という76トン、2本マストのスクーナーがどういう理由で出帆し珊瑚礁で座礁難破してしまったか、その後乗り組みの16人がいかに無人の小島で生き延びたか、が語り言葉で易しく述べられています。明治30年代といえば、すでに日本でも近代の船装備が整えられ、海洋国の活躍を始めていた筈と思ったのですが、かなり興味引かれるプリミティブな場面が多く、そのことだけでも面白いと思いました。また、老練な船乗りから水産講習所の練習生まで様々な16人が、工夫を凝らし智慧を出し合い力合わせて、生き延びる様子は、現在の私達の海での生活に参考に出来ることまであります。特に特異な場面だけに、人間の心理状態を考えた上、行動に生かすことには考えさせられました。ヴェルヌの15少年漂流記は名作の誉れ高い小説で、世界中の子供達が読んでいる本ですが、こちらは、16人おじさん漂流記とも言える実話なので、面白いのは間違いなく、是非目を通して欲しい1冊です。 (by 徳子) |
||||
| (18)海のサムライたち | ||||
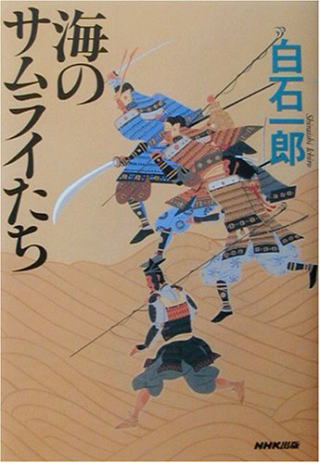 |
著 者:白石一郎 発 行:NHK出版 |
|||
|
先日訃報を聞いた白石一郎、彼の本はほぼ全部読んだつもりだったのですが、2003年出版のこの本がまだありました。しかし長編の物語ではなく、いわば彼が今まで書いてきた小説の要約本ともいえるものです。特に九鬼嘉隆(戦鬼たちの海)、小西行長(海将)、三浦按針(航海者)、山田長政(風雲児)、鄭成功(怒涛の如く)など史実に絡ませながら小説として書き上げたもの(カッコ内が書名)の簡単な紹介が要約として納得させられる本になっています。他には倭寇の名のもとに16世紀、海上武装集団が暴れまわった基とされる松浦党、また日本では最古の海賊と目される10世紀の藤原純友、瀬戸内海の村上水軍の祖、村上武吉のことも書かれていますが、白石一郎によるこれらの長編にはお目にかかっていません。もし誰かご存知でしたら、是非教えて下さい。また藤原純友については著者が白石一郎ではなく、金重明(キム・チュンミン)、“巨海に出でんと欲す”という長編小説があり、同時期の日本を揺るがせた平門将の乱と連動させながら書き進められて、なかなか迫力があります。王女を嫁にした朱印船主と副題のある荒木宗太郎についても、風雲児のなかに記述が少しあるだけ、詳細は分かりません。村上水軍、松浦党について、白石一郎は集団の活躍であったとし、敢えて特別の主人公を描こうとはしなかった節が感じられますが、もっといろいろ書いて欲しかったと、あらためて思いました。 (by 徳子) |
||||
| (19)アメリカ彦蔵 | ||||
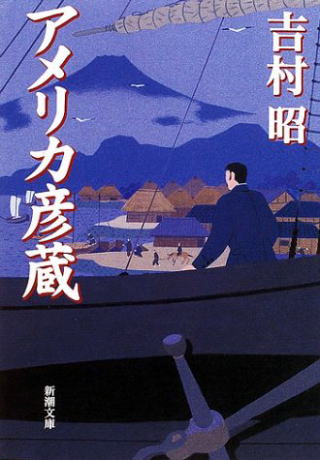 |
著 者:吉村昭 発 行:新潮文庫 |
|||
|
前に“漂流”という本をご紹介しましたが、この作者は、漂流、と言う事実に関心が強く、アメリカ彦蔵と呼ばれた漂流民を通して幕末から維新の時期の漂流史とも言える著作です。幼名彦太郎、後に彦蔵と呼ばれる少年が1800年中期に播磨灘から出港して、当時の典型的な難破船の憂き目に遭いますが、アメリカの貨物船に救出されました。サンフランシスコに着いた後、日本への送還が準備され、永力丸の1行は香港に送られます。ここで日本行きの艦隊司令官ペリーを待つのですが、ペリーの到着は遅れに遅れて、しびれを切らした彦蔵とあと2人はアメリカに戻ることになりました。香港では肥前島原からの漂流民、力松に合い彦蔵たちは日本に帰ることを諦めている顛末を聞かされます。当然音吉達の話にも触れられていて、モリソン号事件のことが復習が出来ました。音吉の助力で永力丸の乗組員達は日本に帰ることが出来ますが、1人だけサスケハナ丸に残された仙太郎こと、サム・パッチと呼ばれた仙八のことまで、史実を突き止めて書かれておりますので、漂流史としての価値が高いと言えるでしょう。サンフランシスコに舞い戻った彦蔵は15歳の少年であったためか、税関長のサンダースに息子のように可愛がられて引き取られ、アメリカの教育を受けました。さらにサンダース夫人の厚意により洗礼まで受けたため、日本帰国に当たってはアメリカに帰化することになりますが、アメリカの生活に馴染んだ彼は、日本人でありながらアメリカの人間として、新しい時代に入った明治期に活躍することが出来ました。この本の筆致は事実を淡々と書き綴っているだけ、の感がありますが、それだけに真実の重みがあって、十分に読み応えがあると言えるでしょう。 (by 徳子) |
||||
| (20)督乗丸の漂流 | ||||
| (イメージ未) |
|
|||
|
10月27日にセントレアで、知多から世界へと題した講演会が行われると聞き、参加を申し込みましたところ、その内容が「中部国際空港はなぜ常滑沖になったか」を基調講演とし、地元に当たる美浜町長が音吉を語り、半田市長が督乗丸の重吉についての講演をするとのこと。急いで督乗丸の漂流についての本を漁り出した次第です。半田出身の重吉(正確には佐久島の生まれ)は、督乗丸の船頭として14人の仲間と1年6ヶ月に亘る長い漂流の苦しみを味わった後、イギリス船に救出され、5年後に故郷に帰還しました。この漂流記は、重吉の話すところを新城の領主菅沼家の家老格に当たる池田寛親が書き取り、「船長日記」として書き上げたものを、分かりやすいように現代文に書き直した本です。更に著者は重吉に関わりあった事柄については、詳しく解説を書き述べ、当時の背景もよく理解できます。漂流という事件は本当によく起こったもので、ひとつひとつを挙げて読み出したらキリがない感じですが、ここでは薩摩の永寿丸という船の遭難者と一緒に日本に送り返される場面があり、永寿丸についてを語るのに、伊勢若松の神昌丸で遭難、ロシアで通訳になっていた新蔵の話も出てきます。漂流記の内容は、江戸時代の風習として神仏に祈り、神籤を引いて現状を占うしかなかったことは、どの本にも書かれ、切ないかぎりですが、特に督乗丸の場合は、みんな漂流を泣き悲しみ、揃って自殺を何度もしようとしたなど、辛い場面が多い上、読み物として面白いとは言えないように思いました。著者の川合氏は、元々運輸省の役人で、海事史専攻の立場から執筆されたようですから、お世辞にも文章がうまいとは言えません。それよりも、鈴木太吉著、「池田寛親自筆本、船長(ふなおさ)日記」は注があるとは言え、文語体の内容が読み辛いにも拘らず、こちらの方が、文学性が高いと評価されている通り読み応えがあります。 (by 徳子) |
||||