 (21〜30)
(21〜30) (21〜30)
(21〜30)
| (21)大黒屋光太夫 | 吉村 昭 | (2005/11/28) | ||
| (22)ニッポン人異国漂流記 | 小林 茂文 | (2006/01/15) | ||
| (23)フィオナの海 | ロザリー・K・フライ | (2006/04/16) | ||
| (24)海・建築・日本人 | 西 和夫 | (2006/09/06) | ||
| (25)海洋の科学 | 蒲生 俊敬 | (2006/09/06) | ||
| (26)われらをめぐる海 | レイチェル・カーソン | (2006/09/06) | ||
| (27)ゴールデン・キール | デズモンド・バグリイ | (2006/09/16) | ||
| (28)黒い海流 | ハモンド・イネス | (2006/10/04) | ||
| (29)ボンベイ・マリーン出帆せよ | ポーター・ヒル | (2006/10/21) | ||
| (30)海王伝 | 白石 一郎 | (2006/11/23) | ||
| (21)大黒屋光太夫 | ||||
 |
著 者:吉村 昭 発 行:毎日新聞社 |
|||
|
またまた漂流記になりますが、ご存知伊勢若松出身の船頭の物語です。江戸時代多くあった漂流者で、幸運にも帰国できた人は少なかったはずですが、その中の1人、しかも地元と言ってよい、身近に思われるために飛びつきました。そして音吉や重吉、そして光太夫の例にある如く、伊勢湾は海運のとても盛んなところだったことが、よく分かります。遭難はどの船も同じような経過を経て、苦難の日々を過ごしますが、光太夫はロシアの威光輝けるエカテリーナ女帝に拝謁の上、帰国が許されました。アムチカトカ島に漂着後、カムチャッカに渡り広大なロシアの大陸を横断、首都サンクトペテルブルグまでの寒さと戦いながら旅する苦労は、読んでいて胸を打たれます。光太夫は帰国後、幕府役人から取調べを受ける中、桂川甫周がその聞き語りを“北さ聞略”としてまとめた記録から、光太夫の話はよく知られることになりました。その中で、恩人とも言えるキリロ・ラスクマンの光太夫に寄せる協力、これはジョセフ彦蔵の親とも言える税関長のサンダースや、中浜万次郎を救出したホイットフィールド船長と同じく、人種を超えた人間愛があり、人との出会いがいかに大切かを教えてくれます。また、光太夫も臆することのない堂々とした態度で、オーナー・スッキパーに見られ特別の待遇を受けることができた上、キリロの日本文化に対する評価を素直に認めていることなど、日本の誇りを感じることもできます。 (by 徳子) |
||||
| (22)ニッポン人異国漂流記 | ||||
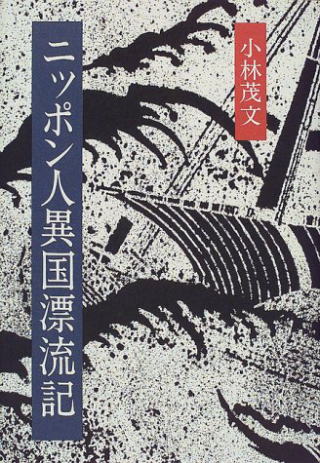 |
著 者:小林茂文 発 行:小学館 |
|||
|
伊勢湾を中心とした、言わば地元に当たる海域の船が、江戸時代に漂流した物語を今まで読んできましたが、総括とも言えるこの本に出会いました。音吉、重吉、そして光太夫らの漂流記は、その苦難が偲ばれ漂流先の異国における様々な体験が、どんなものであったかが興味の対象だったのですが、江戸時代の鎖国体制のなか、漂流という事件に巻き込まれた漂流民がイヤでも認めざるを得なかった日本及び日本人としての認識がいかに形成されたか?をはじめ、信仰のこと、外国の情報がいかに伝えられたか?異国という未知の場所への認識の変化といった分析が、漂流民夫々の体験を伝えながら書き綴られています。確かに信仰心を強く持ち、気持ちを落ち着けることで苦難の漂流を耐えた人たちがいました。この信仰が漂着先で日本人としての自負心の支えになっていたようです。全く見ず知らずの異国の人間を最初、鬼ではないかと想像していたものの出会ってみると、人間はどこの国であろうと同じであると見直すに至る認識の変化もありました。外国の文化に触れて、日本を見返り神国、皇国の意識に呼び覚まされた人もいたと、この本では述べています。ある意味では、悲劇だったかもしれない帰国後の万次郎、ジョセフ彦蔵、彼等は少年期に漂流しアメリカでの教育を受けたがために、日本人として生きるには、アメリカ文化との狭間で葛藤しなければなりませんでした。それに比べて光太夫は、船頭としての統率力が強い力となり、自信に溢れてどんな場面にも対応できた上、帰国後の拘束も緩やかで、異国体験がマイナスにはならなかった人生を送ることができました。 |
||||
| (23)フィオナの海 | ||||
 |
著 者:ロザリー・K・フライ(矢川澄子) 発 行:綜合社 |
|||
|
日本での最初の出版は、1996年ですから、既にかなり古い本ですが、古代ケルト民族にまつわるスコットランド伝説を基として、書かれたものです。子供向けの易しい文章で、北の海辺に生きる少女フィオナを描いている内容が、メルヘンチックなものであるにも拘らず、海の様子はとても、生き生きとして素晴らしい表現で描かれています。また妖精伝説の物語なのに現実感があり、フィオナも彼女の周りの人々、おじいちゃんやおばあちゃんは勿論、現実には有り得ないアザラシに守られて生きてきた弟のジェイミーも、実在の人物として勘違いしてしまいそうですし、北の海に浮かぶ貧しい島も、行ってみたいような錯覚をおこしてしまいます。ダイナミックな冒険物語は面白さが感じられますが、たまにはこんな、優しい童話も読んでみると良いものですね。 (by 徳子) |
||||
| (24)海・建築・日本人 | ||||
 |
著 者:西 和夫 発 行:NHK Books |
|||
| 少し風変わりな書名ですが、建築学の先生が、従来の常識的にいわれてきた日本人は農業民であるとの思い込みを、そうではなく古代から海に関わってきた海民というべき民族であることを主張するために書かれた本なのです。三内丸山遺跡や吉野ケ里遺跡における巨大な柱や物見櫓が、海と関係あるものとして、謎解きのように、理論的な説明を述べ、出雲大社の柱は高く太く、海を見る建築であることの実証をするなど、視点の新しさがとても面白く感じられました。また奥能登の豪農屋敷、時国家の巨大な家は豪農としての権力誇示ゆえのものではなくて、海に由来するものとの研究発表の結果を出しています。日本人が様々に海に関わってきた事例は、日本海を北前船が行き来した賑わいこそ、今ではよく知られていますが、そこにも海を見た建築がいかようであったかを説明し、海とは否応なく関わりをもった島の町や港のことが述べられています。それも建築という視点からの説明がなにか、新鮮さを覚えさせてくれました。ヨット乗りとして当たり前に思っていた海への関心が、どこで、この本にあるような海民のDNAを拾ったのかな?そんなことさえも思ってしまったことでした。 (by 徳子) | ||||
| (25)海洋の科学 | ||||
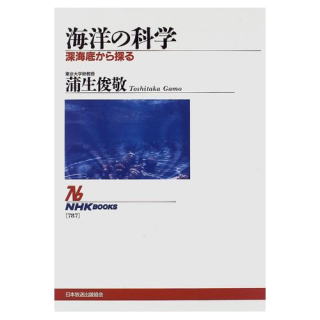 |
著 者:蒲生 俊敬 発 行:NHK Books |
|||
|
前回レーチェル・カーソンの“われらをめぐる海”を読み、海の科学をもっと知りたくなりました。それと彼女が本に書いてから、すでに半世紀も経っていますので、どのような進展があったかも確かめたかったのです。ニュースなどで断片的には知っていましたが、海底は正しく、地球の最後のフロンティアと言えそうです。深海底から噴出している熱水、あるいは冷水であっても海水成分のコントロールや海流の決定に関わっている現象が突き止められ、太陽光線の届かないところでの生物の存在など、内容は豊富です。ただしカーソンの著述と比べると、こちらは単刀直入の筆致で、もう教科書というしかありません。また教科書にありがちな、実験過程あるいはその結果についての書き方は、専門的なきらいがあり、少し面倒くさくて読み飛ばしました。地球の生い立ちにまつわる海底の調査は、とても進歩していて、1996年出版のこの本もすでに時代遅れになっているのかもしれませんが、海についての科学的な知識を持つと言う点では、充分役立ってくれることでしょう。 (by 徳子) |
||||
| (26)われらをめぐる海 | ||||
 |
著 者:レイチェル・カーソン(日下 実男) 発 行:早川書店 |
|||
|
著者のレイチェル・カーソンは農薬の無制限な使用が、環境汚染を引き起こすと訴えて“沈黙の春”を著した、いわば現在のエコリズムを先取りしたことで知られる人です。でも彼女はそれ以前に海洋学者として活躍していました。高校時代に文学を目指したものの、大学では生物学に目が向きこちらを専攻したのですが、そんな経緯からも元々文才があったのでしょう。マサチューセッツ州のウッズホール臨海研究所に勤務した経歴から、“海”を紹介するこの本が書かれましたが、とても表現が文学的なもので、理科系の硬い学術を紹介している本とは思われません。内容は海なるものの実態を、様々な角度から眺めた本質を探っているものです。例えば海の現象のひとつである波を取り上げても、なぜ波が出来るか?どのように動くか?地球上のどこでどのような波が見られるか?といった波の本質を説明する、非常に科学的な内容です。また、博学であることの著述にも感心させられますが、ただ残念だった(?)と言ってよいのかどうか分かりませんが、地球規模の説明が、地図がないために読んでいて、場所の確定ができないもどかしさがありました。これは読む側の、知識不足を曝け出した不勉強のせいとすべきなのでしょうけれど。1950年に出版されて以来、全米でベストセラーを続け、数々の賞にも輝いたというこの本の価値は、その後の学術上の発展による新しい発見や知識の発掘にも拘らず、間違いなく一読に値すると言って良いでしょう。 (by 徳子) |
||||
| (27)ゴールデン・キール | ||||
 |
著 者:デズモンド・バグリイ(宮 祐二) 発 行:早川書店 |
|||
|
物語としては少し古く、第2次大戦中にパルチザンによって奪われたナチスの金塊及び財宝を手中に収めようという、冒険小説です。タイトル通りの、金塊をヨットのバラスト・キールにしてイタリアから持ち出す計画が、この宝を狙うマフィアやごろつき相手に、知恵を絞り用意周到な行動によって計画遂行する過程は、正しく冒険小説そのものです。著者は実際にケープタウンに住み、ヨットについても知識があるとのことで、とても迫力ある描写で、読む者を惹き付けていきます。苦労を重ねた末の結末が、なかなかのもので、面白い!の一言に尽きる本の1冊と言えるでしょう。 (by 徳子) |
||||
| (28)黒い海流 | ||||
| (イメージ未) |
|
|||
|
先回のゴールデンキールに続いて、ヨットを絡ませた海洋冒険小説です。ただし主題は、タンカーからの油流失を発端にした海洋汚染という問題提起の、少し考えると、重い部分が訴えられているようです。描写は生き生きと事故現場、海況あるいは、主人公の心象にいたるまで的確に描かれて、読む者を物語りの中へ引きずり込み、冒険小説の面白さを嫌でも感じさせられました。話は実際にあったかどうか不明ですが、イギリス西部のランズエンド岩場にのし上げた1隻のタンカー事故により海生動物の死滅を見せ付けられた、ここに住む夫婦の格闘ともいうべきもので、妻は流出オイルの阻止を狙って油を燃やしてしまおうと行動を起したのですが、タンカーが爆発して死んでしまう。夫は最愛のパートナーを失った心の拠り所を、事故を起したタンカーの航海士に復讐しようと画策、それがロイド保険の調査員と結びつき、巨大な組織への挑戦となっていきます。現在では海洋汚染に対する各国政府の努力があって、タンカーの船底は2重構造にするとか、タンク内の海水清掃は禁じられるなど対策が講じられていますが、この本が書かれたのは、まさに油による汚染が野放し状態の時期のことで、それだけに問題は重かったのでしょう。しかし今読んでも、小説の面白さは変りません、ぜひ堪能して欲しい1冊です。 (by 徳子) |
||||
| (29)ボンベイ・マリーン出帆せよ | ||||
| (イメージ未) | 著 者:ポーター・ヒル(高岬沙世) 発 行:早川書房 |
|||
|
18世紀ヨーロッパの列強がアジアへ進出するに当たって、当初スペイン、ポルトガルには少し出遅れたものの、イギリスは強力な海軍力によって制海をなし、東インド会社という組織の下、アジア貿易の利を得て海洋国家としてのゆるぎない基礎を築いたことは、歴史上の事実として知られています。この本は、イギリス東インド会社の護衛艦艦長の物語で、会社組織そのものについての新しい発見も得られました。タイトルにあるボンベイ・マリーンというのは、東インド会社活動を阻止する海賊や、フランス・オランダといった敵国からの保護を引き受ける私設海軍のことで、栄光輝けるイギリス海軍に比べるとちょっと、しょぼくれた存在のように描かれています。しかし特命を受けたエクリプス号艦長のアダム・ホーンは、肉体的にも精神的にも、まるで不死身さながら、人員不足をならず者ぞろいの囚人達で補い、使命達成への活躍を見せるのです。あらくれ囚人集団の監視と訓練という特殊状況には、ハラハラ、ドキドキの場面が続きますし、フランス艦との遭遇、戦闘場面では海戦の興奮を感じさせられと、息つく間のない展開には、ただただ先へ進むしかありません。艦長アダム・ホーン・シリーズの第1作目としてのこの本の評価は、ホーン・ブロワーシリーズに並ぶのではないか、といわれたそうですが、間違いなく新海洋冒険シリーズの開幕となっても不思議ではないでしょう。 (by 徳子) |
||||
| (30)海王伝 | ||||
 |
著 者:白石 一郎 発 行:文藝春秋 |
|||
|
久し振りに白石一郎作品を読み返しました。直木賞を受賞した“海狼伝”続編とも言える本です。この所ヨーロッパの海洋冒険小説の面白さに嵌り、ヨーロッパ海洋冒険本に読み耽ってきていたのですが、ヨーロッパのものに劣らず、充分に匹敵するものと言えるでしょう。海狼伝が出たとき、「潮の香がする小説」と表した人がいたそうですが、当を得た評価だったと思います。作家としても活躍の場を敢えて九州に置き、九州沿岸にまつわるテーマで書き続けた海洋小説作家第一人者の真価を、充分に感じることができるでしょう。物語は村上海賊衆のひとりを父親に持つ笛太郎が、自分の身の上を知らぬまま壱岐で海賊となり、玄界灘での村上海賊衆との戦いで捕虜となって、壱岐から瀬戸内、村上水軍の本拠地に移り、小金吾、雷三郎と共に海で生きる上での冒険の数々を物語っている海狼伝からの続編となっています。笛太郎率いる黄金丸が、いよいよ南海に乗り出していく模様が描かれ、登場人物も山の人間あり、タイ人の脱走奴隷あり、またタイで成功を収めた商人ありと多彩ですが、この本が舞台となっている時代は倭寇の跋扈が目立っていました。そして明国海賊の頭目となった倭寇のひとり、笛太郎の父親で人見孫七郎こと馬格芝(マゴーチ)が登場、ついに笛太郎は、故国のことはすっかり忘れ去って明国海賊の頭目になりきってしまっている父親の馬格芝と対決することになってしまいます。笛太郎はそんな父の姿からのせいか、感傷的な感情は持たず、力いっぱいの戦いで勝利して、タイ国からの脱出へ、と少し余韻を残した完結となっています。 (by 徳子) |
||||